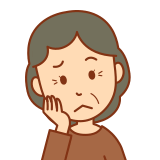
一人で暮らしているのだけど、骨折してしまって動けなくなってしまったの…。こういう時って介護の申請を出せば、助けてもらえるのかしら?
皆さん、色々なきっかけで介護について調べられます。「骨折をして急に動けなくなった」「物忘れが進行している気がする」「転ぶ回数が増えた」「親が心配」「友人に勧められて」など、理由は様々です。
このブログでは、介護保険とは何なのか、どのようなサービスが受けられるのか、私が初めての方にいつも説明する内容や、その進め方をまとめました。
冊子だとなかなか読むのも大変で、よく分からないという方に、簡単にまとめてあります。
参考になれば嬉しいです!
目次
介護保険を受けれる人は?
介護保険は、大きく「第1号被保険者」と「第2号被保険者」の二つに分かれます。
「第1号被保険者」の絶対条件は65歳以上です。
「第2号被保険者」は40歳~64歳で、特定疾病がある方が申請できます。
【特定疾患とは?】
がん(末期)/関節リウマチ/筋萎縮性側索硬化症/後縦靱帯骨化症/骨折を伴う骨粗鬆症/初老期における認知症/進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病/脊髄小脳変性症/脊柱管狭窄症/早老症/多系統萎縮症/糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症/脳血管疾患/閉塞性動脈硬化症/慢性閉塞性肺疾患/両側の膝関節または股関節に著しい変形
を伴う変形性関節症
「何か受けたい介護サービスがある」方なら、とりあえず相談しに行きましょう!
介護認定が降りる人は?
介護サービスを受けたいと思っていても、介護認定が降りないとサービスを受けられません。
(実費なら受けられます)
介護認定の審査は、一次判定と二次判定があります。
一次判定は12項目あるリストの調査結果と主治医の意見書を元に、コンピューターが介護度を判定します。
(3ヶ月以内に医者にかかっていないと、介護認定は受けれません。受けていない方は、申請時に受診してくださいと言われます)
二次判定は介護認定審査会という人による審査会が行われ、最終的な介護度が決まります。
【一次判定の12項目リストとは?】➡全国共通です
身体機能・起居動作
例:麻痺がある、起き上がりや立ち上がりが大変、歩くのにふらつくなど
生活機能
例:階段の昇り降りが掴まるところがないと厳しい、閉じこもりがちなど
認知機能
例:すぐ忘れてしまう、分かっているようで分かっていない、今日が何日が分からないなど
精神・行動障害
例:徘徊・ひとり歩きをしてしまう、昼夜逆転、暴言や暴力があるなど
社会生活への適応
例:買い物するときにお金のやり取りが難しい、薬の管理ができない、電話がとれないなど
排尿・排便
例:トイレに一人で行けない、漏らしてしまうなど
食事
例:食事を摂らない、摂るのを忘れてしまう、自分で食べようとしないなど
清拭・洗髪・入浴
例:お風呂に入ろうとしない、一人で入れないなど
整容
例:一人で顔を洗う、歯磨きをする、髪を整えることができないなど
更衣
例:一人で着替えをすることができない、着替えることを拒否するなど
服薬
例:薬を袋から自分で出せない、何をいつ飲むのか分かっていないなど
口腔清潔・義歯管理
例:一人で義歯を外せない、義歯を洗えないなど
上記のどれか一つでも当てはまる場合、介護認定が降りる可能性があります。

人間不思議なもんで、普段できないのに、審査の人が来るときだけシャキっとされて、自立が出てしまう方もいます。「頑張ったら出来る」は「できる」にされてしまうので、出来ない演技をする必要はありませんが、審査ではありのままの姿を見てもらい、頑張る必要はありません。
「何で出来てしまうんだ!!普段できないのに!!」と突っ込む家族の姿を多く見てきました(笑)
こればっかしは、本人のプライドや緊張もあるので、仕方ないかな…と思います。
そんな時に役に立つのは主治医の意見書です。先生には受診のときに、普段の姿を伝えて、分かってもらっておいてください。
【今からできること】長く付き合え、信頼できる主治医を見つけておきましょう。
介護保険を使って受けれるサービス
受けたい介護サービスが無くても、何かあったときにすぐ使えるように、介護認定だけ取っている賢い方もいらっしゃいますが、認定が降りる可能性も低く、そのような意識高い方は稀です。
介護認定が降りるまでに1ヶ月~2か月ほどかかります。降りるまでは、「暫定」という方法で介護サービスを受けることが出来ますが、リスクもあります。
介護保険で使えるサービスは、大きく分けて「自宅で受けられるサービス」「地域密着型サービス」「施設に入るサービス」の三つです。
自宅で受けられるサービス
自宅で生活していくために受けれるサービスです。受けれる条件は、家で暮らしている方となります。
(×施設に入所している方)
①訪問系サービス➡家に訪問してくれます
訪問介護…介護士(ヘルパー)が訪問し、食事介助・トイレの手伝い・入浴の手伝いなど身体に関する手伝いや、掃除・洗濯・食事を作る・買い物に行くなどの生活支援を行ってくれる
訪問入浴…家のお風呂に入れない方に、浴槽を持ってきてくれて、部屋の中でお風呂に入れる
訪問看護…看護士が訪問し、医療的に身体の状態を見てくれる。先生と連携。
訪問リハビリ…看護士や理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が訪問し、リハビリを行ってくれる
居宅療養管理指導…医師・薬剤師・管理栄養士・歯医者・歯科衛生士が通院が難しい場合、家で診てくれる
②通所系サービス➡通って受けるサービス
通所介護(デイサービス)…家から送迎があり、その場所で半日や1日過ごす。脳トレやレクリエーション、運動、食事、お風呂に入れる
通所リハビリ(デイケア)…家から送迎があり、その場所で半日や1日過ごす。リハビリが中心
③短期入所系サービス…➡短い間だけ、施設に入るサービス
短期入所生活介護(ショートステイ)…家から送迎があり、その場所で1泊以上過ごす。基本的に部屋で過ごす。
短期入所療養介護…家から送迎があり、施設に一旦入所する。看護やリハビリを受けることができる。
④その他
福祉用具のレンタル…電動ベッドや車いす、手すりや杖、歩行器などがレンタルできる
福祉用具の購入…ポータブルトイレやシャワーイスなどが購入できる
住宅改修(リフォーム)…手すりを取り付けたり、段差を無くしたりすることができる
居宅介護支援(ケアマネージャー)…要支援の方は毎月電話+3ヶ月に1回の訪問、要介護の方は毎月訪問してくれて、介護サービス全般の相談をすることができる
小規模多機能型居宅介護…施設が泊まりのサービスを提供しているので、日中はデイサービスに行ったり、施設の部屋に訪問介護や訪問看護が来たり、平日は施設に泊まり、土日は自宅に帰るなど、色々なサービスの盛り合わせができる(訪問系+通所系+施設入所)
施設に入るサービス
介護保険を使って、施設に入るサービスもありますが、施設は本当に色々な種類があり、施設によって特色もバラバラなので、最近は施設紹介サービスを使う方が増えています。
地域密着サービス
地域密着サービスは、その地域に住民票がある方限定で、小規模で行っているサービスです。
(住民票は他の土地で、娘さんの家に住んでいる場合などは利用不可➡住所変更が必要)
通所介護(デイサービス)…定員が18人までと決められています
あまり大人数での団体行動や、たくさんの人と生活することが苦手な方もいます。
そのような方は在宅サービスでも、施設に入る場合でも、地域密着型のサービスを利用しましょう。
介護度とは?
介護認定を受け、介護認定が降りると介護度別に分けられます。
軽い順番に…自立、要支援①、要支援②、要介護①、要介護②、要介護③、要介護④、要介護⑤です。
支援と介護の違いは、支援は何かしらの支援があれば基本的に自分でできる方、介護は支援があれば生活できる方、という見方です。
介護度によって、支給される単位数が違います。
要支援①…5003単位
要支援②…10,473単位
要介護①…16,692単位
要介護②…19,616単位
要介護③…26,931単位
要介護④…30,806単位
要介護⑤…36,065単位
この単位数の中であれば、介護サービスを1~3割負担で受けることが出来ます。
(はみ出た分は10割実費になります。)
大体の目安になりますが、介護サービスを受ける金額です。
訪問介護(ヘルパー)…掃除、洗濯、買い物、調理などの生活支援サービス(20分~45分未満): 約179 単位/回
通所介護(デイサービス)…1回あたり約800~1,200単位
訪問看護…30分以上1時間未満:約823 単位/回
訪問リハビリ…(約20分):308 単位/回
福祉用具…介護用ベッドセット:1500単位
だいたい、1単位1円と思ってもらえればと思います。
介護保険の申請方法

名古屋市は65歳以上の方の申請は電子申請も可能になりました。遠方にご家族様がいて、インターネットに強い方は直接行かなくても申請ができます。
A. 電子申請(オンライン)📱
- スマートフォンまたはパソコンから申請可能。マイナンバーカードと電子署名アプリ(Grafferなど)が必要です。
- 対象:65歳以上
- 申請完了後、受付メールが届き、認定後に「介護保険資格者証」が郵送されます。現在の介護保険被保険者証は破棄してください。
B. 窓口または郵送での申請
- 新規申請/区分変更申請:
→ お住まいの区役所福祉課または支所区民福祉課へ申請書を提出
申請に必要な書類 📄
- 要介護・要支援認定申請書→役所にあります
- 介護保険被保険者証(原本)→65歳になると、全員に送られてきます
- 医療保険の被保険者証 の提示またはコピー(40~64歳以上)
※ 40~64歳の方で医療保険情報が自動確認できない場合、医療保険資格の証明書類の提示が必要になることがあります。
認定調査と審査の流れ 🧾
- 認定申請後、認定調査員が自宅などを訪問し、日常生活や身体・認知状態を確認します。
- 同時に、かかりつけ医による主治医意見書が提出されます。医療状態や介護必要性が記載されており、重要な審査資料となります。
(主治医意見書は、向こうが先生に確認してくれるので、こちらは何もしなくて良いです) - 認定調査票と医師意見書をもとに、介護認定審査会で審査・認定(一次・二次判定)が行われます。
認定結果の受け取り
- 申請から原則30日以内に、認定結果が通知されます(書類不備などがある場合、遅れる可能性あり)。
- 認定が「要支援①~要介護⑤」の場合、介護サービスが利用可能になります。

介護認定が出る前に何かのサービスを使いたい方は、申請した日から遡って介護サービスを使うことができます。しかし、介護度によって使える単位数が違うので、要支援②の上限単位数で考えて使っていたら、結果は要支援①だったという場合、実費が発生するというリスクがあります。
分からないことがあれば、とりあえず区役所か、お近くの地域包括支援センターに相談に行ってください。
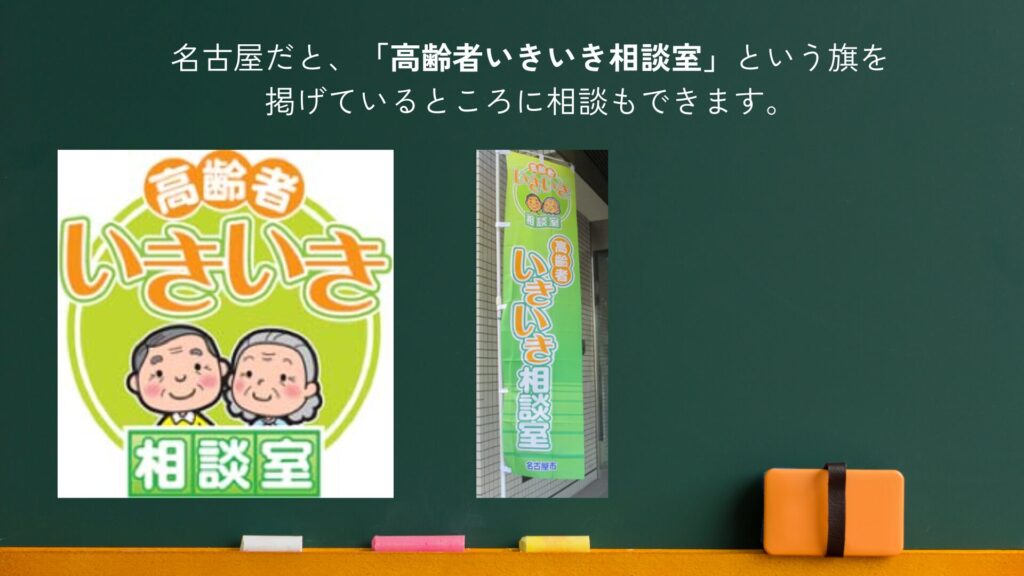
介護保険は使わないのが美学?
私の祖父は、「介護保険は払って使わないのがかっこいい!」と生前言っていました。
しかし、まだ歩けるうちに私が「手すり付けた方がいいよ!」という提案を無視し、一気に車いすに。
確かに、手すりをつけたからといって、悪くならない訳ではありません。
何に困っているのか、それ自体分からずに自分たちで頑張ってしまう方がほとんどです。
「頑張ればできる」は「できない」として、介護サービスに頼ってもらえたらと思います。
「もう無理!限界!」まで我慢せずに、「頑張れば出来るけどキツイ」くらいで使ってもらえれば
いつまでも悪くならずに家で生活できる時間が長くなる可能性が高いです。
甘えと頼ることは違います。
自分でできることは自分で行うことで能力の低下を防ぎ、辛いところは介護サービスを頼って長く家で生活できるようにしましょう!




コメント